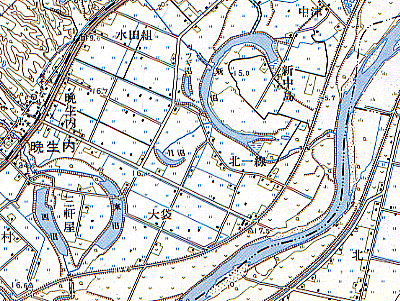|
���L��̎O�����Ύ��ӂ̃c�A�[�u���������������ʗ��_�Ёv �@�@���Ύs�����E���Ύs���}�X�^�[�̉���ē��@�@�@ |
�����F2024�N4��20���i�y�j
�t�̏㋽�W�I�T�C�g�̌��I�㋽�̊�Ղ�̌����悤�I
|
�R�[�X�ē� �@���Ύs����8�F30���i�`���[�^�[�o�X�j��9:30���������11:30�����ʗ��_��(���H�܂�)��14:00����������i�`���[�^�[�o�X�j��15:00���Ύs���� �@�@�@�@���s�\��F7.8�`�A���H�F4.6�`�A���H�F3.2�`�@�@�@���s���F1,8081�� �u���Ύs���}�C�X�^�[�̉�v����̋��͂ŁA���Ԓʂ薳���ɏI���܂����B |
�@�������u���Ύs���}�C�X�^�[�̉��v���ē����u���Ύs�������
���i�W�v�̊��ŊJ�Â�������R�E�H�[�N�u�t�̏㋽�W�I�T�C�g�T���I�㋽�̊�Ղ�̊����悤�I�v�ŏ��L��̗��ꂪ���o�����n�`�₩�Ă̐�̐ՁA�͐�~�Ɍ������ʗ��_�ЂȂǁA���L��Ƌ��ɗ��j�����ꏊ���Ƒ���F�l�ƈꏏ�ɕ����܂��H����̎��ɂƂ��ē���A7km���x���������ł��B�������V�C�\��͐���ŏ����Ȃ�\��I���Ύs���}�C�X�^�[�̉�̕��̈ē�������̂Ŋy���݂ɂ��Đ\�����ށB
�@���Ύs�����ɂ́A�x���͂��o�X�͑S�H�����Ȃ��̂ŁATX�����w���w����������ƂɂȂ�B���s���Ԃ�7���قǁi�j�B
�@8�F30�W�������A8���O�ɒ����Ă��܂��A��20�l�ƈē��l���悹�A���Ԓʂ�s�������o��A�`���[�^�[�o�X��9�����ɐ�������ɓ����B
�@
���F��������Ɍ������@�@�@�@�E�F�������
�@����133�͓���A�����O���H�Ńo�X����~��A���h�Ȗ��ƒʂ�s���ƒ����A�����͗����ŁA���ʓ�����ɓ���A�g�C���^�C���i�g�C���͋����ʗ��_�Ђ܂Ŗ����j�����A�S�����W�����A�����Ŏ��ȏЉ�Ǝ��ӂ̐��������������A�����^���i���W�I�̑��j�A�S���C�͏[���ŏ�����̌��N�Ǘ��Ɋ�������B���R�E�H�[�N�ɂ͌��N����Ԃł��ˁI
�@
��������@�B�e�F202/10/1�Ɉ�x�����ɗ��Ă���
�@�����̌��@�g������ɂ��A�ނ��Ől�C�ł���
|
����������� ���L��̌b�܂ꂽ���R�����������ӌ����ł��B5�w�N�^�[���̉����ɂ́A��A���A��3�̒r���͂��߂Ƃ��āA�����A�ǐ�A��A�A�������A���b���A���ۋ��Ȃǐ��ӂɊ֘A�����{�݂������ƕ���ł��܂��B����ɁA�ӂ��ʂ̓c�����i�����]�ł��鍂���A����₩�ȕ����S�n�悢�Ő��L��������āA�܂��Ɏ��R�Ƃ̂ӂꂠ�����ɂ����S���炮�����ł��B ��錧���Ύs�㋽3190 ���L��́A�ȑO�͎֍s���ė���Ă����̂ŁA���т��ѐ��Q���N���������̂Ɠ����ɁA�×��̂Ƃ��ɐ�������ʂ̓y���͓Ɠ��̒n�`���ł��A��������͏��L��ɂ���Ăł������R��h�̊O���ɂ����镔���ɂ����Ă��邱�Ƃ�������܂��B ���̏ꏊ�i�֍s�͐�̐Ձj�͑傫�Ȏ��n�тł���A��J���~������]���Ȑ����͂��Ȃ����Ƃɂ��X���i�����j��Q���A����œ��Ƃ肪��������ۊQ�ɂ���Q�����Ă����̂ŁA���ɓ����ēy�n���ǂ��s��ꂽ�B�������A���̐ݔ��̘V�����ƈܓx�̐��ʒቺ�����ƂȂ�A�u���c�y�n���Ǒ����������Ɛ���n��v�Ƃ��čēx�̋ߑ㉻���s���A���̎{�݂�2001�N�ɏv�H�����Ƃ������Ƃł��B ���L��Ɛ藣����Ă��邱�Ƃ����O������̌��ƂȂ��Ă��܂��A�����琅�͎��R�ɗ���܂���B ���������u���Ύs���}�C�X�^�[�̉�v�̐搶���A���Ȃ����u�̂́A���͍���������Ⴂ���ɂ�������Ȃ����A���̓|���v�ŋt�ɗ����E�E�E�v�ƁI ���̌̉��Ɍ����Ă���A�ΐF�ň͂�����n��̕������A���݂̏��L��̒�h�ŁA�O�����ɂ͐�̗���Ă���l�q�͂Ȃ��A�{���Ƃ͐藣����Ă���B ��������́u�w��ً}����������邽�߂ɋً}�I�ɔ���ꏊ�v�Ƃ��Ďw�肳��Ă��܂����A����͎w����Ƃ͈قȂ�A�ЊQ�̊댯�����Ȃ��Ȃ�܂ŕK�v�Ȋ��ԑ؍݂���Ƃ����킯�ł͂���܂���B���̒n��̔��ꏊ�́A��荂��ɂ����㋽���w�Z���w�肳��Ă��܂��B ���ꂩ��������A������������L��̐Z�H�ő�n�i���Ƃ��ƍ��䂾�����j����ꂽ�n�`�ɍ��ꂽ�����ł��B |
�@��������ɂ͂����ɖ߂�̂ŋA��Ɋ��̂����m��Ȃ��B���h�Ȍ����ł���A�O�����̐��܂ꂽ�l�q���m�ꂻ�����I
�@
���F��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F���ꂩ��i�ރR�[�X�̐����@�@�O������
�@��������̉��ɂ�����������Ɍ������B���L��̐Z�H�ő�n�������ł����n�`�𗘗p�����ꂽ�����B��������n�̍��͔��������������������A�����i�Z�V�]�j�������Ď��������Ă��������ł����A�Z�H���������ԑ����𑱂���|�����������Ȃ��Ȃ�~�߂������ł��B
�@���̔���������ɂ͔���_�Ђ�����o�X���~�肽���̐�ɓ���������܂��B
�@
�@������������Ɍ��āA�����̑�n����Ⴍ�Ȃ������c�̒������u���ꂩ��i�ރR�[�X��O�����̂ł���l�q�v�����������܂����B�̂����L��͎֍s���Ă��̕ӂ𗬂�Ă������A�֍s�����^�����ɗ���A�c�����������c��A�O�������ɂȂ��������ł��B
�@���̕ӂ肪��w���n�Ŏ��R��h�ƌĂ�鏊�������ł��A�ڂ̑O�̑傫���㋽�t�H�[���̋��Ɂi�u�����h���j�̗��ɑ傫�ȋ���h�A�����͉E�ɋ���h�ɓo��K�i�����邪�A�ē��l�͂����͒��i�B
�@
���F����p�r���@���@�Δ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F���c�Ɣ��Α����O�����ł���
�@���i����������p�r���@���Ƌ��͓��ł���A�O�����̗p�r���@��ŁA�����Ō����鐅�c�ɐ��𗬂��Ƃ̂������ł��B
�@���ɑ傫�ȐΔ肪�����u�ыo�����v�i������䂤�䂤�j�u���앨�Ȃǂ��A���Ɛ����悭�������邳�܁v�Ƃ���A�u�сv�͈�┞�Ȃǂ̈Ӗ����Ă���B
|
�������� �@�����̐��c�́A���L��̂������Ȃ̂ɐ��c���ێ����邽�߂̐��s�����������Ƃ��A�����Y����}�g�R�̉���ʉ߂��A����s�̂����ցA�����Ĕ_�Ɨp���E�H�Ɨp�����p���B�㐅���p���Ȃǂɗ��p����Ă���B�����㋽�ɂ�������ł���B �@�����͒}�g�R�̂ӂ��ƂɈʒu���A���̉��₩�ȓ��͌ΖʂɁu�t���}�g�v���f��B���̖����Ƃ��Ă��m����B�}�g�R�̓o�R���Ō��O�g�C���E���ԏ�̂���A�������x�����p���Ă���B �@�S���ÁX�Y�X���c�͌��݂Ǝv���Ă����̂ł����A�����ǂ����痈���̂��͂��ꂼ��̐��c�̂��ꂼ��̗��j������̂Œ��ڂ��������̂ł��B |
�����ł͎O�����͂܂��܂��ڂɐG��Ȃ��A�ē��l�炪�����Ȃ�t�ɐi�݁A���߂���������h�ɓo��K�i��o�肾���A����p�r���@��Ɣ��̎O�����Α��̎{�݂Ɍ��A�����ď��߂Ď��B�͎O�����߂邱�ƂɂȂ��B
|
���k�C�����S�s�E���ˌS�Y�P���i�T�����̂P�n�`�}�u����v�j��
�O������ �@���̒n�`�}�ɂ����Ύ��́A�������Q�U�Qkm�̑傫�Ȑ�ł��B�����ȍ~�A�^�����߂Ɣ_�n�����̂��߂ɉ͐���C���ϋɓI�ɍs���܂����B���̌��ʁA�͐쉄���͖�T�Wkm���Z�k����A�������̐��ʂ͂R�D�Tm���ቺ���A�_�n���}���ɑ��������Ƃ����܂��B�n�`�}�Ɍ�����O�����́A���̖��c�ł��B �@���݂́A�n�蒹�̔n�Ȃǂ̎c���ꂽ���R�Ƃ��āA���邢�͎s���̌e���̏�Ƃ��Đ�������Ă��܂��B�����̌��n�͐�̗��H��z�����Ȃ���A�n�`�}��̎O�����Ɩ{���̏�����ǂ��Ă݂�ƁA�����ǂ����u�֍s�v�������܂��B |
�@
���F�O�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F���L��̒�h�ɓo��
�@����h����O�����߂�A����Ȃ����L���ł��B�z���ȏ�̏��Ŕ������Ƃ͌����Ȃ����A���R���n�̐l�X�̐����ɑ傫���e���B��璭�߂�ƎO�����Ɍ����邪�A�������炾�ƍL�����ƍs�������i�ł��B
�@���͋���h�����珬�L��̐V��h�ɓo��A�����œ��ɗp�ӂ��ꂽ�K�i�͖����A���̐V��h���u�����ʗ��_�Ђւ͐l�����ꂽ��h�v�Ɓu�����ڂ����v�̑�n��ʂ��Đi�ނ悤�ł��B
�@
���F���ɎO�����������@�}�g�R�������܂��@�@�@�@�E�F�L���r�����
�@�܂��Ȃ��A�L���r������ł��A���L��ƎO�������q�����Ă���Ȃ����ł��B
�@����E���i�Ђ���j�E��ԁi�Ђ���j�͂��̂悤�ɏ��L��ƎO�������q���{�݂ŁA�����ł��L���r������ƌĂ�Ă���悤�ł��B�O�����Α��͐��c�ŁA�����瑽���̐����g���Ă䂭�����ł��ˁI���c�ł́u���납����Ɓv�������Ă��܂����A�����̐��c���x�k�������Ȃ��Ă���悤�ŁA������������̐��c���ڂɕt���܂��B
�@���L��ECCTV���r���ɗL��܂����B���L����L�c��V��t���]�߁A�k�������}�g�R�B�����̕����傫�ȏd���܂������Ă����A�O�������������A���L����������A���N���N�ƕ����A�������������E�E�E������u�d���ł��ˁE�E�E�v�̐����o���Ȃ��ł���ƁI
�@����ȃc���C���Ɂu���̎ʐ^�͉�������E�E�E�E�v�u�}�g�R����3�̕�E�E�E3�̕�̖��́E�E�E�v�܂��u���̎R�E�j�̎R�v�u�j�̎R�E���̎R�v�̌�������ς��B�e�ꏊ���B�s�肩��́u�j�̎R�E���̎R�v�ɕ���Ō����A�V��R�͂͂����茩���Ȃ��B���̉��H�E���H�����ٓ��E���E�傫�ȑ܂������Ă���ޏ��I�E�E�E����ł������ʗ��_���܂Łu��ꂽ�ƁE�E�E�v�Ƃ͌����Ȃ����ł��B
�@
�����ڂ����E�����{��
�@���H�͎O���������L��������Ȃ��u�����ڂ����v�ɓ���A�W�X�ƕ����̂݁A���������傫�ȍH���������邾���B�E�ɂ����L�������A�L�����Ă���A���ɍk����A���镨�͌��܂��Ă���悤�ł��B
�@����Ȏ��A�����{�݂����̍����ɂ���A�擱����l�̑����~�܂�A�������n�܂�B���������x�߂鎞�ԁA���̏ꂪ���H�E���H�̕ʂꓹ�̂悤�ł��B
�@
���F�L�c��V��t�@�ʐ^�̒����ɁI�@�@�@�E�F�����ʗ��_���̐X�������ė���
�@�����ڂ������珬�L��̌����A�L�c��V��t��������悤�ɂȂ�A��4.6�`�̕��H���I�ՁA�ŏ��̓����̎O���H�������ʗ��_���̗��Ȃ̂ŋ߂��Ă��A�����̓p�X�B
�@����133�i�����j�����h���Ă��铹�ƕ������������o��A�������E�܂������ʗ��_�Г�����ʉ߁B
�@
���F�������i�ӂ��炢���j�@11�F26�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F�L�c��V��t
�@�����ŁA�������A�����Ɍ������i�푍�@����294���j�ƐV�������i����123�j�E�g������B�㗬�ɂ͖L�c��V��t(�푍�s�n��𗬃Z���^�[)��������B
�@�����̗ǂ��V�C�ł����A���̕��ɓ����Ă��}�g�R���m�F�ł��܂���ł����I
|
���������� �������͋����L���ł��B���̋��͂��đ����̎Q�q�҂��Q�q�̍ۂɓn�������̂ł���A�l�E���痋�_�̎Ђ̂���n�ւƏ����Ă����悤�Ȋ��o�𖡂킦���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���݂͋������班�����ꂽ�ꏊ�ɋ����˂����Ă���A���Ă̂悤�Ȋ��o�𖡂키���Ƃ͓����������܂��A���̒����ɗ��Ɛ_�Ђ⏬�L��A�}�g�R���܂߂��i�ς����n�����Ƃ��ł��A�푍����̍L�傳�������邱�Ƃ��ł��܂��B 1928�i���a3�j�N�ɉ˂���ꂽ�R���N���[�g�̋��B�������͏푍�s���Ƌ����ʗ��_�Ђ���������œ��ɍl�������̂ł͂Ȃ��悤�ł��B�����{��k�Ђ�2011�N����3�N�Ԃ͒ʍs�~���A�����g����ʂ��ԂɌ���B1964�i���a39�j�N�ɉ͐�@�������ɂȂ�O�́A�_�БO�ɂ͈��H�X�ȂǑ����A�͐�~���ɏZ��ł���A���L��𗘗p�������^�����������悤�ł��B1964�N�͓����I�����s�b�N�A���厡�E�쑺����E��Q�ȂǁB���{�̌o�ϐ������ے����Ă�������ł��B |
�@�ȉ��A�����ʗ��_���̂��b�ł��F
�@
�����Q���������܂��@�@�@�@�@�@�@�@��̒���
�@
�����ɓ���܂��@�@�@�@�@�@�@�@��̒���
�@
�����ʗ��_�Дq�a
�����ʗ��_���i���Ȃނ�킯�����Â�����j�́A���Ύs�����A���Ύs�㋽�̏��L��Ȃ̒�O�n�ɒ�������B
���ˎs�̕ʗ��c���_�A�Q�n���q���̗��d�_�ЂƂƂ����֓�3���_�Ƃ����B�n���ł́u���_���܁v�Ƃ��Đe���܂�Ă���B
�@
�q�a������
�@�����A�q�a�̍��̎Q�W�a�ɓ���A��L��o��n��q�a�ɓ���A�q�a�̈֎q�ɍ���A�u�`������������B
�@
�@�e�V��̊G��͋I��2600�N�L�O���ƂƂ����A�攌�Ƃ��Ă�������X��{�i�����S�����X���Ċ��|�i�������j�������̂ŁA�S����`�������A1942�i���a17�j�N�Ɋ��������B�{�i���g�ɂ��V���͑S���I�ɂ���ϒ��������Ђ̏d��ƂȂ��Ă���B
�@���̗��h�Ȕq�a�����ɓ��点�Ē����A�d���q���ł��A�����ʁI
�@
�_���}�@�A�A
|
�@�������Ƌ{ �z����̓�ʂ̓V��G�s�_���}�t �z����̒����̊ԁi�ʘH�j�̓V��̂Q�ʂ����藳���~�藴�́s�_���}�t�������Ă���A���藴�͔����ɂ݂̗��A�~�藴�͎l���ɂ݂̗��ƌ�����B���݂́A��̊O���i�쑤�j�ɂ���̂��~�藳�A��̓����i�k���j�ɂ���̂����藳�B �@���ɏo�����������̂ł��B |
�@
�_���}�B�A➃
�@
���F�g�߂ȓV���@�@�@�@�@�@�@�@�E�F����
�@�{���g�̓V����ɂ́A�^�P�m�R��X�C�J�Ȃǐg�߂ȕ����`����E�E�E�E�}�g�R��w�i�ɔn�̓V�����G������Ă���B�K�C�h�u�b�N�ɂ͔K�E�{���f�ځB�V��悪����̖{�ɂȂ�����f���炵���I
�@
�@��12���A40���̒��H�^�C���A����ɉ���A����ɖ{�a���Ղ��A���̉��ɗz���˂����݊������Ί_�ł��ɂ�����B�����œ����l�ɂ���������ƁA�t�N���E�̎ʐ^�����ߘA����������荞��ŁA����邩�Ƒ҂��Ă���l�̘b������������B5�����q�i��������A�����`�����X���Ƃ����B�ނ�ɕ������A�����́i���j�܂��e���猩�Ă��Ȃ��Ƃ����A�t�N���E�͂��Ύs�̒��Ɏw��A����������s�����ɑ����u���Ă���܂��i�A�e�i�̐����j�B
|
�������ʗ��_�Ё� �@��������̌i�ϐ}�A���܂ŎR���̗��e�ɂ͗��فE����������30���قǂŁA�����O���i�Ƃ肢�܂��܂��j�̖�O�����h���āA���Ղ�Ɋւ�薳���Q�q�҂ł��ӂ�Ă��������ł��B�֓���k�Ђ܂ł͗y�������s������_�ސ���ʂ���Q�q���������悤�ł��B�t�E�H�̗��Ղɂ́A�Q�q�҂̍s���X�Ƒ����Ă����Ƃ����܂��B �@���A��h�������グ����A�܂��͐�@�ɂ�茚�ݏȁi���y��ʏȁj�̎w���̉��A�l�Ƃ�D��ɒ�h�O�Ɉړ���]�V�Ȃ�����܂����B���_�Ђ��ړ]�̘b�������������ł����A����Ȍo��Ƌ{�i����ړ]�����܂��Ă������Ƃ�����A�l�̏Z�܂Ȃ��_�Ђ͐扄���ɂȂ����悤�ł��B �@����́A���݂̌i�ς́A�Ж����E�_�y�a�����܂ދ������Ɖ͐�~�ɒ�������S���ł����������̂ɂȂ��Ă��܂��B �@��J���~��Ƌ����͍������ߕ��C�ł�����h����̓��H���������ČǗ���ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B�������A�x�d�Ȃ鏬�L��̔×��ł���Гa����Q���������Ƃ͗L��܂���B�B��A1986�i���a61�j�N�̏��L�쌈��̎��ɂ͋����܂Ő������܂������A���̎��ł���Гa�����ɐZ���邱�Ƃ͂���܂���ł����B �@���{���\�����F��{�{����i�a�̎R���c�ӎs�{�{���{�{�j�͌��X�F���̒��B�Ɍ�Гa���������Ă������A�����̑�^���ŗ�����Ă��܂����݂̍���Ɉڂ��Ă���B���������ʗ��_���͏��L��̒��B�ɂ��邪�A���т��т̑����ŋ������Ǘ�������Гa�͍����ʒu�i�W��17�b�j�ɒ������Ă��邽�ߔ�Q�ɑ��������Ƃ��Ȃ��I �@���̏��L�쌈��i1986�i���a61�j�N�j�̎�����39�A���ÑI��̓����h���E�}���\���ŏ��D���B���������i���b�e�j�͎O�����̎���ł��B ���A�e�i�̐����� �@�t�N���E�́A�u�p�m�v�u�m�b�v�u�`�����v�ƌ����A�t�N���E�́A�u�A�e�i�̐����v�ł��B �����āA�t�N���E�́A�A�e�i�̏ے��Ƃ���钹�A�A�e�i�͝D�̒m�b�̕�����Z�p���i��A�p�Y�̎菕�������Ă��܂��B���̃A�e�i�����ɕϐg���A���̎p�����t�N���E�������ɂȂ����ƍl�����Ă��܂��B �@���Ύs�̑I�藝�R�F �_���E�l�������\���钹���X�̓N�w���Ƃ������Ă��܂��B�m�b�ƋZ�p�̏ے��ł���A�w���s�s��i������Ύs�ɂӂ��킵�����ł��B ���i����i�悤����j |
�@
�����x��̏W���ꏊ�@�萅��
�@�Q���ґS���W���A�q�a�̗��ɂނ����B
�@
���F�{�a�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F�������i������������j
�@�{�a�͍�Ɉ͂܂�Ă��邪�A��錧�̎w�蕶�����B�����ɉ��ɋ����Ђ̒��������������Ă���B
�@
���F���̏��@�u�_�r�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F�|�_�㐛�@�����V��
�@�����������A�O��2020/10�ɖK�ꂽ���̓J���J���ł������A�����͐������܂��Đ[�������܂������A�ɐ��Łu�_�r�v�ł��B���̍��ɖ߂�ߓ����L�邪�A�����ċ�����������A�\�ɂł�A�|�_�㐛�����V�����u����A���̔�̑O�ŒS���҂��ߌ�̕������C�ɍĊJ���Ă��ꂽ�I
|
���|�_�㐛�@�����V�聄 �@�|�_�㊯�@�����V��́A1793�i����5�j�N����A���̒n�ɂ������㊯���ɕ��C�����|�_�O�E�q�咼���i�Ȃ����j�̓����Ɋ��ӂ��邽�ߌ������ꂽ���́B
�u�|�_�㐛�@�����V��v�ƍ��܂�Ă���B �@�����A�V���̋Q�[�ɂ��r�p���Ă������̒n���𗧂Ē������߁A�_�ƐU����}�邽�߂̊��_�����i�߂��B
�܂��A������ƂȂ�l���𑝂₷���߁A�Ԉ������֎~���A�o�Y������{�痿��^���A���l����ƌL�▜�\���x�������B �@1814�i����11�N11��8���A77�ŖS���Ȃ�ƁA�|�_�㊯�̌������㐢�Ɏc�����ƁA��1815�i����12�j�N3���A���̔肪�������ꂽ�B
�܂��A�q���̌��S�Ȉ琬�ɓw�߂����Ƃ���A�ߔN�̐M�ł͂��邪�A������̑O�ɂ́A�u�q��E�q��Đv������A ���̔���Ȃł���q��Ɍb�܂���Ƃ����B���͍�77�A���E�ł��I �@����͎Ⴂ�j�����Q�����Ă���A�Y����������x�Ɋ������ė~�������̂ł��B |
�@
��{�̑傫�Ȗ�
�@���̂܂ܓ�E��̒����Ɍ������Ǝv�������A��l�̐A���S���҂��A���ނ�ɓːi���čs���s�v�c�ł��B��E��̒����̊Ԃ̎Q���͍����ƂȂ��Ă��邪��̒����߂��ɑ�P���L�A��G�m�L������B
�܂��A��̒����߂��ɂ͓��U�A���������ꂼ������A�s�v�c�Ȕޏ��ł��I
�@�Ƃ��낪�I�������ē�����S���҂͑�҂��M�d�Ȑ��ށA�����ʗ��_�Ђ́A���������o140�x�����ʂ�p���[�X�|�b�g�ł�����B�u��̒��������̎G�ؗт���_�y�a�̓����t�߂ɔ����Ă���v�Ƃ̎��ł��B
|
���o140�x���́A�{���q�ߐ��ʁi�O���j�b�W�q�ߐ��j���瓌��140�x�̊p�x�𐬂��o���ł���B�k�ɓ_����k�ɊC�A�A�W�A�A�����m�A�I�[�X�g�����[�V�A�A�C���h�m�A��ɊC�A��ɑ嗤��ʉ߂��ē�ɓ_�܂ł����ԁB���o140�x���͐��o40�x���Ƌ��ɑ�~���`������B�s�v�c�Ȗ��͂ɂ��ӂ��ꏊ�ł����B |
�@���o140�x���H�i���w���̎��w�ԁj�Ǝv�����E�E�E���ނ�ɓːi���čs���ޏ���ǂ��A��G�m�L�̑O�ɗ����A�I�I�����T�L�̐����B��G�m�L�͗Y�E���̉Ԃ��قȂ�A���Ԃ��������i�ΐF�j�ł��A�����ɃI�I�����T�L������Ă��邻���ł��B
|
�I�I�����T�L ���L��́A�S�{�삪�R�n����̗���Ȃ̂ɑ��āA���c�̐��̏W�܂�ł��B���������āA���L��̉͐�~�ɂ͖L���ȓy�낪�͐ς��A���炷��A���w���S�{��̍��I�͌��ɔ�ׂĂ����ƖL�x�ł��B���L��̓����I�Ȏ��،Q�Ƃ��ăJ���R�M�J�G�f�̌Q���A�����I�I�����T�L�̐H���ƂȂ�N�k�M��G�m�L�̌Q���A����ɍ������ăS�}�L���_�݂��Ă��܂��B���{�ނł́A�m�E���V���q���A�}�i�A�q�m�L�J�T�A��Ɏw�肳��Ă���t�W�o�J�}�A�����ĕ���13�N�ɏ��߂Ċm�F���ꂽ�L�^�~�\�E�̑�Q���������܂��B�S���I�ɂ͌���������A�������炵�Ă���M�d�ȋ�ԂƂȂ��Ă��܂��B �@���ނ́A�������A�����A�L�c���̂R�剁���͂��ߑ召�����̎搅�����݂����A�k���������n���܂Łi�R���I��肩��X�����܂Łj���������~�߂��A�S���ʂ��ė��ꂪ���₩�Ȃ��Ƃ���A�t�i�A�R�C�A�I�C�J���Ȃǂ������������܂��B �@�͐�~���̎��،Q�́A�S�{�쓯�l�Ɂu�`���E�T�M�v���̊i�D�̉c���n�ƂȂ��Ă��܂��B�^���s�𗬂�鏬�L��ł́A���������Ă����u�z�I�A�J�v�̔ɐB���m�F����Ă��܂��B �@�͔ȗт̓I�I�^�J�̂�����ƂȂ�ƂƂ����T�V�o���̏��^�̖ҋח����c�����Ă��܂��B�܂��A�A���A�T�P���k�シ��͐�Ƃ��ėL���ł��B����������ҋחނ��v�w�Ŕ��ł��܂����ˁI �@���L��ӂꂠ�������F�I�I�����T�L�̐X�����邪�B���L��̉͐�~�𗘗p���������v��5���̓|�s�[�A10�����{�ɂ̓R�X���X���炫�ւ�����ł��B �@��錧���Ȏs�̃}�X�R�b�g�L�����N�^�[�u�V���������v�͖{���G���[�l�������f�U�C���ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A���̎q�̂悤�Ɍ����邪�A�H�̖͗l�̓I�X�̂��̂ł���B |
�@�I�I�����T�L�̎p�͒}�g�R��s��ł��ȑO�͗ǂ��ڂɂ�������ǁA���͂Ȃ��Ȃ����ڂɂ�����܂���B
�@���B�͎Q���ɖ߂炸�A�������ɏo�āA�A�H�ɐi�݂܂��B
�@
���F�����{�݂������ė���@�@�@�@�@�@�@�@�E�F���H�̎O������
�@�����{���������A���ɑ傫���}�g�R�u�j�̎R�A���̎R�v�̕��сA�V��R���m�F�ł��܂��B
�@���̐����{�݂̎�O�����H�E���H�̕����ł��A�E�ɉ���Ɛ��c�n�тŋx�k�c���ڂɕt���܂��A�����̌����������ςł����A�Ẳ��i�E�l�ޕs���E�E�E�B
�@�L���c���A�����ڂ�������ł��A�u�㋽�̊�ցi��Ձj�A�����悤�v�ƌ����Ă��E�E�E�E��ւ͋����ʗ��_�Ђł݂����悤�ł��I
�@�㋽�̑�n��т͈�Ղ���R���z�A�ꕶ�l�������ȏW��������ĕ�炵�Ă��������ł��B�u�_�Ў��ӂ̓c��ڂ␅�c����ꕶ�E�퐶����̓y�킪���܂��Ă���A�ȒP�Ɏ��o���ꂽ�����ł��i�_�Ђ̋{�i����̂��b�j�v�B���������u�ق�A�ق�E�E�E�v�Ɠy��̌��Ђ��w���܂����A��������E���]�T�͗L��܂���i�j�B�Ȃ�ł���Ւ����͍s���Ă��Ȃ����̗l�ł��E�E�������Ă�������@�邩�I�E�E�B
���x�͍����O�������������Ă��܂��B�}�g�R�͐i�ފp�x�Ō�����ʒu�����E�ɕς��I
�@
���F���_��@�@�@�@�@�@�@�E�F�n���ω���
�@�O�������̒�h�ɏオ���������A���Ă͗{�\�Ƃʼnh�������������A���j�E�����̒~�ς��������悤�ł��B�h�����{�\���ׂ����������ꂽ�̂Ńr�b�N���i���O��������ςł����I�j�A��z�͖L���Ȓ~�ς��������悤�ł��B���Z���܂Ŏ��Ƃł͗{�\�����Ă���A�{�\�Ő������тė����̂ŗǂ�����܂��B
�@�O�������琅�c�������ď��ō�Ƃ̘e��ʉ߂��A�n���ω���������A�������̎R���ɓ����l�Ȕn���ω��肪�������A�����̑�n�ł��n�̗͉͂^���ɑ傫���𗧂������Ƃ�����܂��B
�@
���F��͍L��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�F���ɂ��N�������L�^
�@�吳�\�N���H�ƔN����������ł���܂����B
�@�n���ω���̗��̍L��ɂ́A���F�̃N�T�m�I�E�A�������̃n�i�_�C�R���i�V���J�b�T�C�j�����W�B�A���ώ@��ɂȂ��āA���ӂ̐l�������l�ł��ˁI
�@���̌�́A�A���ώ@�𑱂��Ȃ���A�|�M�Ȃǂ����Ȃ���A���c�̉E����ʉ߂��A��������ɓ��炸�A�E�Ɍ��������āA�Ăѐ��c�������āA����p�r���@��̒��ԏ�̃`���[�^�[�o�X�ɏ�肱�݁A���Ύs�����ցB
|
����������� �@��������ɂ́A�g�C���ɗ������l�݂̂ʼn���ʉ߁A���߂āA�x�e���Ԃ��Ƃ�A��������ʉ߂����������A�c�O�B���Ύs�̌�����4�Ԗڂ̍L�������āI |
|
���g�������
�g������@�B�e�F2020/10/2 �@�g����������L��̎O�����ŁA�ނ�l�œ��키�A�쉺�����a�����߂�������L��X�|�[�c�������L�����Ă���A�X�ɓ쉺�𑱂��������������������ł��B���Ύs�������炱�����߂��̂ŁA���Ύs�����E���Ύs���}�X�^�[�̉��Ńc�A�[����悳���ł��傤�I ���L��X�|�[�c���� �Z���F��錧���Ύs���Ǔc455-1 �A�N�Z�X�F���G�N�X�v���X���u�����L�O�����w�v����ԂŖ�9�� �d�b�ԍ��F029-847-6757 ���ԏ�F���� 76�� �x�ٓ��F�e�j�X�R�[�g�A�싅��Ƃ���12��28������1��4���܂� |